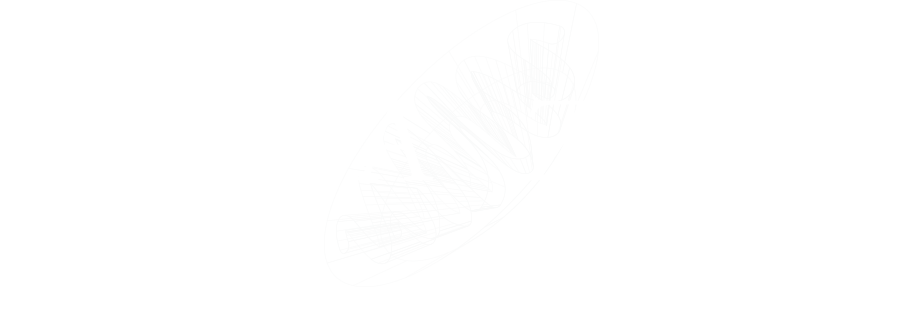
会社概要
社名
アクア・ゼスト株式会社
AQUA ZEST Corporation
設立
2011年11月22日
Established on 22th November, 2011
代表者
代表取締役 亀井一郎
President: Mr. Ichiro Kamei
資本金
1,350万円
事業内容
ライフサイエンス事業における研究開発
Research and development in the field of life sciences
主席科学顧問
麻布大学名誉教授 佐俣哲郎
Honored Prof. of Azabu University, Dr. Tetsuro Samata
所在地
本社・植物工場
〒214-0034神奈川県川崎市多摩区三田2-3227 明治大学地域産学連携研究センター 305
Head Office and Plant Factory
Technology Incubator of the Center for Collaborative Innovation and Incubation, Meiji University, 2-3227 Mita, Tama-Ku, Kawasaki, Kanagawa, 214-0034 JAPAN
細胞科学・免疫学研究準備室
〒152-0003東京都目黒区碑文谷3−12−5 YUI HOUSE B-1
Preparatory office for the researches of cell science and immunology
YUI HOUSE B-1, 3−12−5 Himonya, Meguro-Ku, Tokyo, 152-0003 JAPAN
受賞歴
公益財団法人 川崎市産業振興財団主催
81回 川崎ビジネスオーディション ビジネスシーズ賞&はまぎん賞(横浜銀行賞)
Award of Buisiness Siez and Yokohama Bank A public interest incorporated foundation organized by Kawasaki Industry Foundation
81th Kawasaki Business Ordition
「第5回イノベーションリーダーズサミット(ILS2017) 後援:経済産業省」において、
大手企業からの人気上位100社「TOP100 STARTUPS」に選出
At "The 5th Innovation Leaders Summit (ILS2017), sponsored by Ministry of Economy, Trade and Industry",
we were selected as one of the top 100 most popular venture companies (TOP 100 STARTUPS") from major companies.
所属団体
かわさき水ビジネスネットワーク
Kawasaki Business Network for Water
http://www.kawabiznet.com